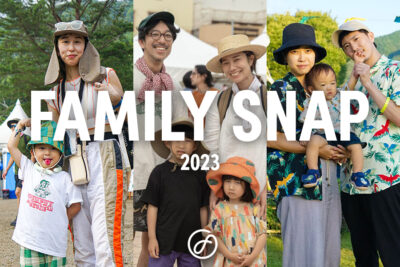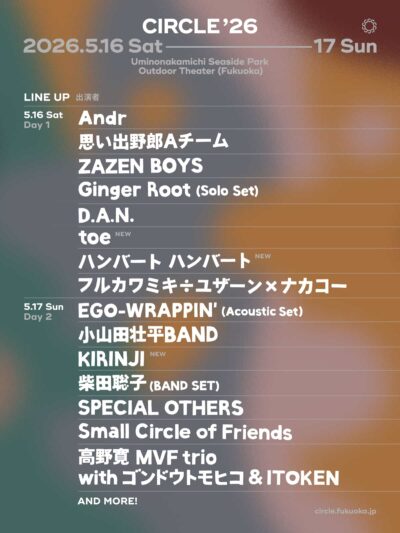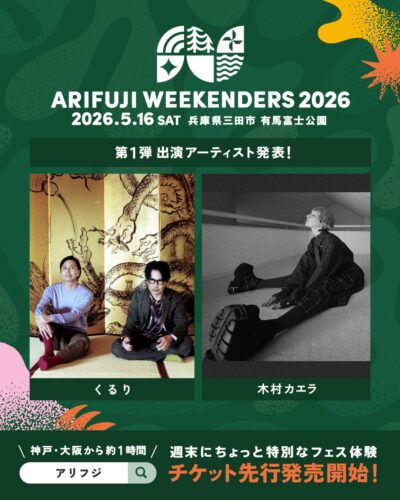2005年に横浜でスタートした「GREENROOM FESTIVAL」は、海のカルチャーと音楽、アートをつなぐフェスティバルとして20年にわたって歩み続けてきた。
「Save The Ocean」をコンセプトに、サステナブルな取り組みを重ねながら、国内外の多彩なアーティストを迎え、カルチャーとコミュニティの場を育んできた。2020年にはコロナ禍による中止、2021年には厳しいガイドラインのもとでの開催と、困難な時期も乗り越えてきたGREENROOM(グリーンルーム)。
そんなフェスが、いま20周年という節目を迎える。例年に増して豪華なアーティストが集う今年は、ジェイコブ・コリアー、カマシ・ワシントン、YG・マーリー、ルディメンタルらが出演。横浜赤レンガ倉庫を中心に、特別な3日間が繰り広げられる。
初の試みとなる金曜日(前夜祭)のステージには、祖父にボブ・マーリー、母親はローリン・ヒルというレガシーを引き継いだYG・マーリーの初来日ライブを中心に、サンセットタイムから夜へと続く極上のナイトマーケットが展開される。「フェスに行く」というより、「横浜の夜に立ち寄る」という感覚で楽しめる、新たなグリーンルームのかたちだ。
本稿は、2019年に実施した周年インタビューの続編として、主催・釜萢直起氏、制作統括の吉田知寛氏、制作・PRを担当する小島歌織子氏による鼎談を通して、この20年の歩みと、”音楽フェス”としてのグリーンルームの進化、そして未来への展望を紐解いていく。
Text/Photo:船津晃一朗
Edit:津田昌太朗
完全復活を経ての20周年構想
─本日のインタビューでは改めて、コロナ禍以降の「GREENROOM FESTIVAL」を振り返っていきたいと思います。そして今回は、釜萢代表に加えて、制作統括を担当されている吉田さん、制作・PRの小島さんも迎えて、多面的なお話をお伺いさせていただければと。まず、吉田さん、小島さんに自己紹介をお願いします。
吉田:自分はGREENROOM FESTIVALの運営・制作や全体管理、アーティストのブッキングを担当しています。グリーンルームには10年以上関わっていますが、それ以前は舞台系の仕事をしていました。もともとカルチャー全般が好きなのですが、特に音楽は背景やその文化も含めて好きで、グリーンルームなら自分がこれまでやってきたことを好きな方面に生かせるなと思って、ジョインして今にいたります。
小島:私は吉田をサポートする形で、制作や行政調整などを担当しています。現在はPRにも関わっています。グリーンルームにはコロナ禍前のタイミングで吉田に誘ってもらって、姉と一緒に行きました。そのときにその世界観も含めて素敵なフェスだと思って、そこから入社させてもらった形ですね。
──フェスの全体像を作り上げながら現場を最前線で支えている吉田さん。コロナ禍の2021年2月にジョインし、その混乱の中で支柱になった小島さん。そして、主宰の釜萢さん。みなさんそれぞれの視点からグリーンルームについてお伺いできればと思います。今年は、コロナ禍で中止となった2020年から5年というタイミングでもあります。
釜萢:2020年を振り返ってみると、5月開催をいったん9月に延期しようとしましたが、最終的に中止になりました。いま思い返せば、当時の判断が正しかったかは難しいところですが、夏フェスシーズン前だったこともあり、たくさんの問い合わせを受けた記憶があります。
──グリーンルームは非常に難しい立場にありましたよね。他のフェスの判断材料にもなっていた印象です。
釜萢:そうですね。そして2021年、その時のガイドラインを守ってキャパシティを半分に抑えながら、ようやく開催に漕ぎつけました。ただ、海外アーティストの招聘は難しく、2022年もその状況は続きました。それをようやく打破できたのが2023年。本当に嬉しかったですね。もともと国内外のアーティストをミックスするのがグリーンルームのスタイルだったので、ようやく本来の形に戻れたという実感がありました。
──コロナ禍でのチームの雰囲気はどういう感じでしたか?
吉田:イベントをやると釜萢が決めたら、迷わず開催モードに切り替えていました。大前提として、過去にしっかりイベントを開催してきた実績があるので、行政との信頼関係もあり、そこは強みでしたが、ルールが日々変わるなかでの調整は本当に大変でした。2021年は相当疲弊しました。できると思ったのにできない、このルールを追加したら本当にお客さんが楽しめるのかなど、調整は難航しました。
小島:どうすれば開催できるかを常に考えながら、ガイドラインと照らし合わせて動いていました。言葉選びひとつにも神経を使いましたね。
釜萢:あと、2019年のインタビューでも話していたけど、自分たちのフェス以外でもオリンピックのサーフィン会場の制作に携わることが決まっていたんです。それももちろん延期。2021年は一時期やれる兆しが見えたんだけど、直前に無観客での開催が決まって。
吉田:あのときは本当に大変でしたね。
──当時、釜萢さんにお話をお伺いする機会がありましたが、リアルで集まれることの価値について、実感と共に語っていただきました。
釜萢:2021年になんとかフェスを開催できたときに、マスク越しでも、お客さんの笑顔が伝わってきた。その瞬間のことは覚えています。仕事の8割が一気になくなってしまった中で、会社が持ちこたえられるかという不安もあった。でも、あの日、お客さんが帰ってきた光景を見た時の喜びが印象に残っています。
吉田:あの頃は「人が集まること=悪」、「お酒=悪」、「フェス=悪」みたいな風潮もあって、自由に動くこともはばかられた時代。それでも踊ってくれたお客さん、出演を快諾してくれたアーティストたちには感謝しかないです。
小島:フェスがいかに非日常を必要とされているかを、肌で感じました。
釜萢:そして、2022年は国内勢のみで開催、2023年は海外勢もブッキングできたけれど、すべてが完全復活したなという実感があったのは、実は去年だったのかも。
“音楽フェス”としてのグリーンルーム
──完全復活の昨年を経て、今年20年目を迎えるのですが、20周年の構想はいつ頃から練っていたんですか?例えばコロナ禍以前と比べて、ここ数年は会場がディスコ仕様になったりと、非日常感がパワーアップしていると感じます。
釜萢 考え始めたのは2~3年前からですね。コロナ禍という特殊な状況があったものの、ステージのスペックを毎年高め続けてきたおかげで、世界的アーティストの招聘も実現できるようになりました。素晴らしいアーティストに出演してもらうにあたって、こちらもその用意をしなくちゃいけない。20年かけて、音楽フェスとして、そのレベルにようやくなれた感覚があります。
──コロナ禍以前と以降でお客さんも変わってきたような気がします。グリーンルームを”カルチャーフェス”だと初期から強調されているのは大前提としてあるのですが、ここ数年で”音楽フェス”としてのパワーもさらに強くなっていると思います。
釜萢 海やストリートのカルチャーを追い続けてきて、ある意味で成熟を迎えたのかもしれません。イベントを開催し続けているから、その積み重ねも大きい。お客さんも年齢を重ねてきて、かたやZ世代のような若いお客さんも増えてきた。カルチャー好きも、純粋な音楽好きも、幅広く受け入れられるフェスに成長したのかなと。
──横浜・赤レンガという場所で開催していることもグリーンルームのスペシャルな部分ですよね。昨年秋の「LOCAL GREEN FESTIVAL」には、横浜を代表するOZROSAURUSが出演して、周年の助走のようにも感じられました。
釜萢 「東京」ではなく「横浜」で続けられたことは大きいです。歴史的建造物を背景に、ライブとマーケットが楽しめるブロックパーティー的な無料エリアと、優雅に極上の音楽が鳴る有料エリアがある。その両方の感覚を持っているのがグリーンルームの特色だと思っています。